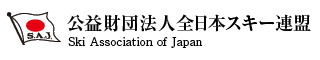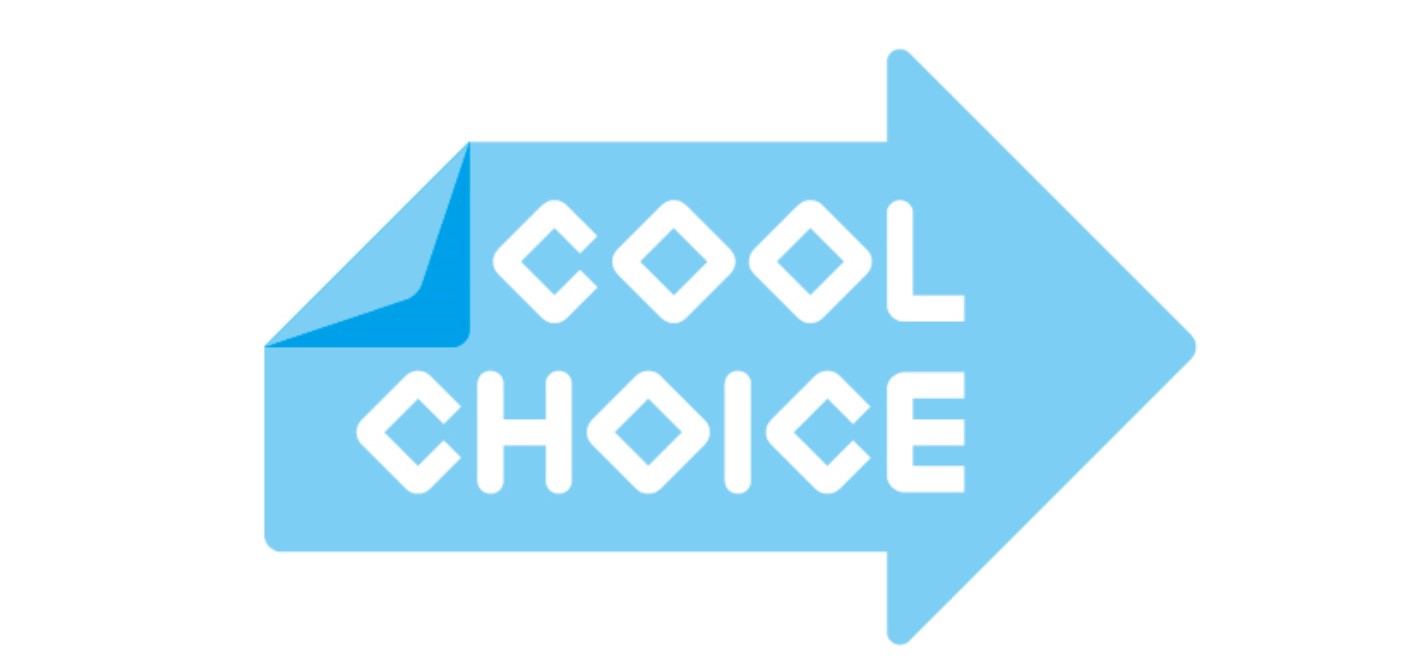| 1922年(大正11年) | 大日本体育協会(現在の日本体育協会)内にスキー部が設けられる |
|---|---|
| 1923年(大正12年) | 第1回 全日本スキー選手権大会が北海道・小樽市郊外の緑が丘で開催される |
| 1924年(大正13年) | 第1回 冬季オリンピック大会(フランス・シャモニー)が開催 第2回 全日本スキー選手権大会が新潟県・高田(現在の上越市)金谷山で開催される |
| 1925年(大正14年) | 2月15日、全日本スキー連盟設立(加盟20団体)。初代会長に稲田昌植が就任 全日本スキー連盟が全日本体育連盟に加盟 |
| 1926年(大正15年)(昭和元年) | 全日本スキー連盟が国際スキー連盟(FIS)に加盟 |
| 1927年(昭和2年) | 『スキー年鑑』創刊 |
| 1928年(昭和3年) | 第2回 冬季オリンピック大会(スイス・サンモリッツ)開催。日本初参加。伴 素彦、麻生武治、竹節作太、矢沢武雄、永田 実、高橋 昴の6選手が代表に |
| 1929年(昭和4年) | 全日本スキー選手権大会に「複合」が新採用 |
| 1930年(昭和5年) | スキーの名手、ハンネス・シュナイダー(オーストリア)が来日。全国各地でのスキー指導行う(アールベルグ・スキー術) |
| 1931年(昭和6年) | 第1回スキー講習会実施(文部省主催) |
| 1932年(昭和7年) | 第3回 冬季オリンピック(アメリカ・レークプラシッド)開催。ジャンプで安達五郎が8位と健闘 |
| 1933年(昭和8年) | 札幌・大倉山シャンツェ(ジャンプ台)が完成。当時の最長不倒距離は51m |
| 1934年(昭和九年) | 1940年の冬季オリンピック、札幌への誘致が決定 |
| 1936年(昭和11年) | 第2代会長に小島三郎就任 第4回 冬季オリンピック(ドイツ・ガルミッシュ=パルテンキルヒェン)開催。ジャンプの伊黒正次が入賞目前の7位(当時は6位まで入賞) |
| 1937年(昭和12年) | 全日本スキー選手権大会の第1回アルペン大会が滋賀県・伊吹山で開催 第5回 冬季オリンピックの開催地が札幌に決定 |
| 1938年(昭和13年) | スキー指導員制度制定 第5回 冬季オリンピック札幌大会は日中戦争の勃発により開催返上 「一般スキー術要領」発刊 |
| 1939年(昭和14年) | 第1回指導員検定会が五色沼(福島県)で開催。11人の指導員が誕生する スキー技術章検定の1~2級が制定される |
| 1940年(昭和15年) | 「スキー・フランセ」、「今日のスキー」邦訳出版される |
| 1941年(昭和16年) | 4月23日、全日本スキー連盟が財団法人の認可受ける(厚生大臣認可) |
| 1942年(昭和17年) | 第二次世界大戦勃発のため財団法人全日本スキー連盟解散。財団法人大日本体育協会スキー部として活動する |
| 1945年(昭和20年) | 財団法人全日本スキー連盟再始動 |
| 1946年(昭和21年) | 第1回地方競技会、札幌と蔵王で開催 指導員検定試験再開 |
| 1947年(昭和22年) | 指導員検定講習、技術章検定制度の再開(1~3級) |
| 1948年(昭和23年) | 日本、第5回冬季オリンピック(スイス・サンモリッツ)に不参加 戦後初の国民体育大会冬季競技大会/全日本スキー選手権大会(第3回)が長野県・野沢温泉村で開催 |
| 1949年(昭和24年) | 『スキー年鑑』7年ぶりに復刊 日本初の風洞実験が東京大学第二工学部で実施される(のちにスキージャンプ競技の練習に使用) |
| 1950年(昭和25年) | 後楽園の特設ジャンプ台で、ジャンプ及び回転の競技会開催。雪は新潟県から貨物列車で輸送(30車両分) 『基礎スキー教科書』発刊 |
| 1951年(昭和26年) | 財団法人全日本スキー連盟、国際スキー連盟に復帰 |
| 1952年(昭和27年) | 全日本スキー選手権大会と国民体育大会が分離開催となる 指導員研修会制度が制定される |
| 1953年(昭和28年) | 全日本スキー選手権大会でアルペンの新複合競技が廃止となり、アルペンは滑降と回転の2種目となる |
| 1954年(昭和29年) | 第3代会長に小川勝次就任 |
| 1955年(昭和30年) | フランススキー連盟へ片桐 匡、橋本茂生を派遣〈目的はアルペン競技の視察とインタースキー(バルディゼール)への初参加〉 |
| 1956年(昭和31年) | 猪谷千春が、第7回冬季オリンピック(イタリア・コルティナダンペッツォ)のアルペン競技・回転で、冬期オリンピックの日本人初メダル(銀メダル)を獲得 全日本スキー選手権大会のアルペン競技が、滑降・回転・大回転の3種目となる |
| 1957年(昭和32年) | 『オーストリアスキー教程』の日本語訳版を発刊 全日本スキー選手権大会第60回記念式典、青森県・大鰐町で開催 |
| 1958年(昭和33年) | 第4代会長に木原 均就任 アルペン世界選手権大会(オーストリア・バドガシュタイン)で猪谷千春が銅メダル(回転)を獲得 アールベルグ・スキー学校長であり、当時オーストリア職業スキー教師連盟会長だったルディ・マットが来日。万座、伊吹山、石打、岩原、赤城、日光、細野の各会場で指導者講習会を開く 全日本スキー選手権大会、アルペンの富井初子がアルペン史上初の三冠王 |
| 1959年(昭和34年) | 『SAJスキーテスト』発刊 |
| 1960年(昭和35年) | オーストリアのスキー指導者ルディ・マットを招き、技術研修を実施 |
| 1961年(昭和36年) | 第1回スキー大学開催 全日本スキー選手権大会でアルペンの富井初子が2度目の三冠王 |
| 1962年(昭和37年) | 第6回インタースキー(イタリア・モンテボンドーネ)開催、日本から4名派遣 |
| 1963年(昭和38年) | オーストリア国立スキー学校のシュテファン・クルッケンハウザー教授、フランツ・フルトナーら2名と来日、各地で講演会開く |
| 1964年(昭和39年) | インタースキー派遣デモンストレーター選考を兼ねた、第1回SAJデモンストレーター選考会開催(福島県・五色沼) |
| 1965年(昭和40年) | 第7回インタースキー(オーストリア・バドガシュタイン)に、初めてデモンストレーター5名を派遣。平沢文雄、宮沢英雄(新潟県)、北沢広明、丸山庄司(長野県)、斎藤成樹(群馬県) FIS理事に木原 均会長(当時)が就任 SAJが国際スキー教育連盟に加盟 佐藤和男、全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技で初の三冠達成 |
| 1966年(昭和41年) | 第11回冬季オリンピック、札幌に決定 ノルディック世界選手権大会でジャンプの藤沢隆が90m級で銀メダル獲得(ノルディック初のメダル獲得) |
| 1967年(昭和42年) | SAJ公認スキー学校制度制定 オーストリア国立スキー学校のクルッケンハウザー教授再来日。日本各地で研修会を開催 丸山仁也が、全日本スキー選手権大会でアルペン男子初の三冠王 |
| 1968年(昭和43年) | 第5代会長に元東京都知事の東 龍太郎就任 第10回冬季オリンピック(フランス・グルノーブル)に、初めて女子選手の代表が出場。大杖美保子(アルペン)、加藤富士子(クロスカントリー)を派遣 |
| 1969年(昭和44年) | FIS理事に伊藤義郎就任 『SAJスキー教程』発刊 |
| 1970年(昭和45年) | ノルディック世界選手権(チェコ・ビソケタトリ)、70m級ジャンプで笠谷幸生が銀メダル獲得 |
| 1971年(昭和46年) | 札幌オリンピックプレ大会開催。23ヶ国が参加 |
| 1972年(昭和47年) | 第11回冬季オリンピック、札幌で開催(35か国参加) 70m級ジャンプで日本がメダル独占の快挙。金メダル・笠谷幸生、銀メダル・金野昭次、銅メダル・青地清二 |
| 1973年(昭和48年) | 5月24日、SAJが財団法人として文部大臣の認可を受ける 日本初のワールドカップが苗場スキー場(新潟県)で開催。柏木正義が回転で10位を獲得し、初のワールドカップポイント(1点)を獲得 |
| 1974年(昭和49年) | 第45回宮様スキー大会がFIS公認の大会となる |
| 1975年(昭和50年) | 第6代会長に伴 素彦就任 第11回インタースキーの日本大会開催が決定(1979年・蔵王) ワールドカップ苗場大会2度目の開催 |
| 1976年(昭和51年) | 富士重工業株式会社より、初めて海外遠征用のチームカー(SUBARU)の提供を受ける |
| 1977年(昭和52年) | ワールドカップ富良野大会開催 第1回ジュニア選手権大会始まる |
| 1978年(昭和53年) | アルペン世界選手権大会(スイス・サンモリッツ)で、海和俊宏が回転で入賞目前の7位 |
| 1979年(昭和54年) | FIS副会長に伊藤義郎就任 第11回インタースキー大会開催(山形県・蔵王) SAJ、国際パトロール連盟に加盟 |
| 1980年(昭和55年) | 第13回冬季オリンピック(アメリカ・レークプラシッド)開催。70m級ジャンプで八木弘和が銀メダルを獲得 ジャンプ・ワールドカップ札幌大会開催。八木弘和が日本選手初のワールドカップ優勝 全日本基礎スキー選手権大会とデモンストレーター選考会を分離 |
| 1981年(昭和56年) | 第1回全日本フリースタイル選手権大会、志賀高原サンバレースキー場(長野県)で開催 クロスカントリー全日本スキー選手権大会で、早坂毅代司が3年連続三冠達成 『全日本スキー教本』、『初級スキー教本』発刊 |
| 1982年(昭和57年) | 『日本スキー教程』一部改訂 |
| 1983年(昭和58年) | ワールドカップ・ノルディックコンバインド日本大会初開催(札幌) |
| 1984年(昭和59年) | 初の国際スキーパトロール大会開催(長野県・車山高原) |
| 1985年(昭和60年) | ノルディック世界選手権大会(オーストリア・ゼーフェルド)開催。ジャンプ団体で日本が6位入賞(渡瀬弥太郎・佐藤 晃・西方千春・秋元正博) |
| 1986年(昭和61年) | 第7代会長に堤 義明就任 第1回冬季アジア大会が札幌で開催 『日本スキー教程』全面改訂 |
| 1987年(昭和62年) | アルペン・ワールドカップ(ボスニア・ヘルツェゴビナ/サラエボ)の回転最終戦で、岡部哲也が日本選手初のラップタイムを奪い(2本目)、4位に入賞 |
| 1988年(昭和63年) | アルペン・ワールドカップ(ノルウェー・オプタル)の回転種目で岡部哲也が日本選手初のアルペン・ワールドカップ表彰台となる2位に入賞 全日本スキー選手権大会のアルペン女子で、川端絵美が史上初の4種目制覇(滑降2戦・スーパーG2戦・回転・大回転6戦すべて優勝) |
| 1989年(昭和64年)(平成元年) | アルペン世界選手権大会(アメリカ・ベイル)で川端絵美が日本女子初の滑降5位入賞 ノルディック世界選手権大会(フィンランド・ラハティ)、15kmフリーで佐々木一成が入賞目前の7位と健闘 |
| 1990年(平成2年) | アルペン・ワールドカップ(オーストリア・シュラドミング)で、岡部哲也(回転)が2度目の表彰台(3位) |
| 1991年(平成3年) | 第18回冬季オリンピックの開催地が長野市に決定 ノルディック世界選手権大会(イタリア/ヴァル・ディ・フィエンメ)で、ノルディック・コンバインド団体が初の銅メダルを獲得(阿部雅司・三ヶ田礼一・児玉和興) |
| 1992年(平成4年) | 第16回冬季オリンピック(フランス・アルベールビル)ノルディック・コンバインド団体で初の金メダルを獲得(三ヶ田礼一・河野孝典・荻原健司) 『SAJスキーチーム・メディアガイド』創刊 |
| 1993年(平成5年) | ノルディック世界選手権大会(スウェーデン・ファールン)で同一大会では初となる金メダル3個を獲得。〈NC荻原健司、NC団体(河野孝典・阿部雅司・荻原健司)、ジャンプ原田雅彦〉 ノルディック・コンバインドの荻原健司が初のワールドカップ総合優勝飾る アルペン・ワールドカップ(オーストリア・サンアントン)、滑降女子の川端絵美が3位で初の表彰台 アジア初のアルペン世界選手権大会、岩手県・盛岡市雫石町で開催 |
| 1994年(平成6年) | 第17回冬季オリンピック(ノルウェー・リレハンメル)でノルディック・コンバインド団体が2大会連続金メダルを獲得(河野孝典・阿部雅司・荻原健司)。個人でも河野が銀メダルを獲得 同大会、ジャンプ団体も1980年以来となる銀メダルを獲得(西方仁也・葛西紀明・岡部孝信・原田雅彦) ノルディック・コンバインドの荻原健司がワールドカップ総合2連覇果たす クロスカントリーの佐々木一成が全日本スキー選手権大会で歴代1位となる通算26勝を達成 |
| 1995年(平成7年) | ノルディック世界選手権大会(カナダ・サンダーベイ)、ノルディック・コンバインド団体で金メダルを獲得、五輪、世界選手権大会4連連覇達成(阿部雅司・荻原次晴・荻原健司・河野孝典) 同大会、ジャンプ・ノーマルヒルで岡部孝信が金メダル。斉藤浩哉は銀メダルを、団体でも銅メダルを獲得。(安崎直幹・斉藤浩哉・西方仁也・岡部孝信) 荻原健司、ワールドカップ総合3連覇 第15回インタースキー、長野県・野沢温泉村で開催 |
| 1996年(平成8年) | 6月29日、SAJ創立70周年記念式典開催 第1回国際スキー技術選手権大会開催(長野県・野沢温泉村) |
| 1997年(平成9年) | フリースタイル世界選手権大会、長野で開催 長野オリンピックのプレ大会となるワールドカップ開催。クロスカントリーで青木富美子(5㎞C)が日本選手最高となる5位入賞 |
| 1998年(平成10年) | 第18回冬季オリンピック長野大会開催 ジャンプ(団体)、ジャンプ(ラージヒル)、フリースタイル(モーグル)の3種目で金メダル獲得 【メダル獲得者と入賞者】 金メダル:船木和喜〈ジャンプ(ラージヒル)〉 岡部孝信・斉藤浩哉・原田雅彦・船木和喜(ジャンプ団体) 里谷多英〈フリースタイル(モーグル)〉 銀メダル:船木和喜〈ジャンプ(ノーマルヒル)〉 銅メダル:原田雅彦〈ジャンプ(ラージヒル)〉 ※クロスカントリー男子リレーで同種目初となる7位入賞(蛯沢克仁、今井博幸、堀米光男、長濱一年) |
| 1999年(平成11年) | SAJ副会長兼専務理事の八木祐四郎がJOC会長に就任 ノルディック世界選手権大会(オーストリア・ラムソウ)開催。ジャンプ(ノーマルヒル)で札幌オリンピック以来2度目の表彰台独占を達成(金:船木和喜、銀:宮平秀治、銅:原田雅彦) 宮平秀治は同大会で出場した3種目でメダル獲得(ノーマルヒル:銀、団体:銀、ラージヒル:銅) |
| 2000年(平成12年) | 5月、オーストリアスキー連盟と協力協定締結 |
| 2001年(平成13年) | 八木祐四郎副会長兼専務理事(JOC会長)9月9日逝去 フリースタイル世界選手権大会(カナダ/ウィスラー・ブラッコム)で、モーグルの上村愛子が同種目日本人初となるメダルを獲得(銅メダル) |
| 2002年(平成14年) | 第19回冬季オリンピック(アメリカ・ソルトレーク)開催。フリースタイル・モーグルの里谷多英がオリンピック2大会連続メダル獲得(銅メダル)果たす 同大会クロスカントリー男子(50kmクラシカル)で今井博幸が史上最高の6位入賞(男子2大会連続入賞) 荻原健司、引退 ジャンプ女子チーム結成 |
| 2003年(平成15年) | 1月12日を「スキーの日」に制定(関連6団体) アルペン・ワールドカップ(スイス・ヴェンゲン)で佐々木 明がゼッケン65番から2位入賞。ラップタイムに0.04差はこれまでの最少差 フリースタイル・ワールドカップ(アメリカ・ディアバレー)で、モーグルの上村愛子が初優勝 |
| 2004年(平成16年) | 第8代伊藤義郎が会長に就任 スノーボード・ワールドカップの女子ハーフパイプ(イタリア・トリノ)で山岡聡子が女子初となるハーフパイプ総合優勝 フリースタイル・ワールドカップ(イタリア・トリノ)で、瀧澤宏臣がスキークロス総合優勝 猪谷千春、三浦雄一郎氏がSAJ名誉委員に荻原健司氏が同顧問に就任 「基礎スキー」から「スキー」へ、「技能テスト」から「スキーバッジテスト」へ教育本部が大幅に改組、刷新 |
| 2005年(平成17年) | 6月26日、財団法人全日本スキー連盟創立80周年記念式典、開催 スノーボード・ワールドカップで、女子ハーフパイプの成田夢露がハーフパイプ総合優勝 |
| 2006年(平成18年) | 第20回冬季オリンピック(イタリア・トリノ)開催。アルペン男子回転で皆川賢太郎4位、湯淺直樹7位と2人が入賞(猪谷千春の銀メダル以来50年ぶり) 同大会で初採用のスノーボードクロスで、藤森由香が7位入賞 |
| 2007年(平成19年) | スノーボード世界選手権大会(スイス・アローザ)ハーフパイプ國母和宏、山岡聡子がともにスノーボード史上初となる銀メダルを獲得 ノルディック世界選手権大会(札幌)でジャンプ団体銅メダル獲得(栃本翔平・岡部孝信・伊東大貴・葛西紀明) |
| 2008年(平成20年) | フリースタイル・ワールドカップで5勝を挙げた上村愛子が初のモーグル総合優勝 クロスカントリー・ワールドカップ(スウェーデン・ストックホルム)の女子スプリントで夏見円が日本選手初の表彰台(3位) |
| 2009年(平成21年) | ノルディック世界選手権大会(チェコ・リベレツ)でノルディック・コンバインド団体金メダル(小林範仁・加藤大平・渡部暁斗・湊 祐介) 同大会でジャンプ女子初採用。最高位は渡瀬あゆみの10位 同大会でジャンプ団体2大会連続銅メダル(栃本翔平、岡部孝信、伊東大貴、葛西紀明) 同大会のクロスカントリー女子チームスプリントで夏見 円・石田正子組が同種目史上最高となる4位入賞 フリースタイル世界選手権大会(福島県・猪苗代町)開催。上村愛子がモーグル・デュアルモーグルの2種目を制し、西 伸幸と伊藤みきも銀メダルを獲得、フリースタイルで初の4個のメダルを獲得 スノーボード世界選手権大会(韓国・カンウォン)で、男子ハーフパイプの青野 令が同種目初の金メダル獲得 |
| 2010年(平成22年) | 第9代会長に鈴木洋一就任 第21回冬季オリンピック(カナダ・バンクーバー)クロスカントリーで女子初入賞となるリレー8位(夏見 円・石田正子・福田修子・柏原理子) |
| 2011年(平成23年) | 東日本大震災の発生により、3月11日以降の国内公認大会の多くが中止に。フリースタイル・ジュニア世界選手権大会の選手派遣も見送り 「I LOVE SNOWキャンペーン」の一環として、SAJ主動の「復興支援活動」を展開 |
| 2012年(平成24年) | 第1回ユースオリンピック(オーストリア・インスブルック)でジャンプ女子の髙梨沙羅、スノーボード・ハーフパイプ女子の大江 光が金メダル獲得 ジャンプ・ワールドカップで伊東大貴が初優勝含むシーズン4勝、ノルディック・コンバインドの渡部暁斗も同様に4勝をマーク ジャンプ女子のワールドカップがスタート。髙梨沙羅が蔵王大会で初優勝 |
| 2013年(平成25年) | 7月30日、内閣府より「公益財団法人」の認定を受ける ノルディック世界選手権大会(イタリア・バルディフィエンメ)のジャンプ競技で初採用された男女混合団体で日本金メダル(伊藤有希、伊東大貴、髙梨沙羅、竹内 択) ジャンプ女子・ワールドカップで髙梨沙羅が8勝を挙げ、初の総合優勝 フリースタイル世界選手権大会(ノルウェー・ヴォス)で伊藤みきがモーグル・デュアルモーグルとも銀メダルを獲得、スキーハーフパイプの小野塚彩那も同種目初の銅メダル獲得 |
| 2014年(平成26年) | 第22回冬季オリンピック・ソチ大会開催 日本チーム史上最多の7個のメダルを獲得(銀メダル4個・銅メダル3個) ジャンプの髙梨沙羅選手がワールドカップ史上2人目となる2連続総合優勝を果たす |